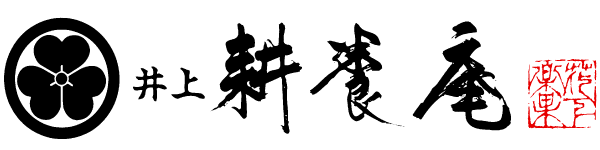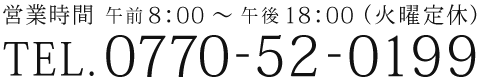2018年8月発行

かつて二条院讃岐(にじょういんのさぬき)は、
生没年もよく分からず、別人と混同されていたりして、
不明の部分が多かったのであるが、
歴史の第一級資料である九条兼実(後法性寺関白)の日記
『玉葉』を紐解くとそこには、公私にわたる記録として、
その記述が長寛二年(1164)から正治二年(1200)に及んでいる。
この時期は、奇しくも院政から武家政治へと政治体制が変動した時期と重なっており、
歌合や源平合戦などについても多数の記述がある。
このことから『玉葉』は、讃岐が生きた平安時代末期から
鎌倉時代初期の様子を窺い知ることが出来る格好の資料であるだけでなく、
兼実の援助を受けて五十九歳頃に歌壇に復帰した讃岐の人と形を考える上で、
重要な書物となる。該本には、「余女房讃岐」とあり、
兼実は讃岐を本妻として手許に置いておきたかったことなどが知られる。
讃岐は、「沖の石の讃岐」として『百人一首』に採られていて、
女流歌人としての地位も確定している。
生没年は、永治元年(1141)頃に生まれ、
建保五年(1217)頃に七十六歳で没したのではないかと、
近年の研究では考えられている。
父は、治承四年(1180)に高倉宮以仁王に平家討伐の「令旨」を勧め、
源平合戦の端緒を開いた源三位入道頼政であり、
母は、源斉頼の娘である。さて、福井県の小浜市に関連すると言われている、
讃岐が詠んだ次の短歌であるが、実は三種の短歌があり、
第一句の「わが恋」を「わが袖」に直したのは、
『千載和歌集』撰者の藤原俊成の手によるものである。
また、『百人一首』では「かはくまぞなき」が、
俊成の子で撰者である定家によって、「かはくまもなし」に変更されている。
わが恋はしほひにみえぬおきの石の人こそしらねかはくまぞなき
(『二条院讃岐集』)
わがそではしほひにみえぬおきの石の人こそしらねかはくまぞなき
(『千載和歌集』)
わがそではしほひにみえぬおきの石の人こそしらねかはくまもなし
(『百人一首』)
【歌意】私の袖(恋)は、潮が引いたときにも海の中に隠れて濡れていて、
いつも見ることが出来ない沖の石のようである。他人は知らないであろうが、
いつも涙にくれて乾く間がないのです。
この歌から、宮城県多賀城市が『百人一首』ゆかりの歌枕である
「沖の石」所在地として知られ、近年の東北大震災で、
沖からこの石が姿を現したところから、
地元ではいつにも増して熱く比定地として語られている。
しかし、小浜市が全く「沖の石」の比定地として縁がない訳ではない。
たとえば、江戸時代の歌人であった
香川景樹(明和五年・〈1768〉~天保十四年・〈1843〉)は、
文政六年(1823)刊の『百首異見』(国会図書館)の中で、
これは頼政の所領であった若狭国遠敷郡矢代浦に、
実際にあった大石のことだとした。これを受けて、
近代の評論家で、『百人一首』(『百人一首』新潮文庫・1976)にも
造詣の深い安東次男(大正八年〈1919〉~平成十四年〈2002〉)は、
『百首通見―小倉百人一首全評釈―』(集英社・1973)の中で、
「潮干に見えぬ沖の石」とは、父である頼政の
日陰の身を気遣う心を寄せて讃岐が詠んだのではないかとした。
たしかに、小浜市の田烏には讃岐の居館跡が残り、
永源寺には讃岐の菩提が祀られており、
讃岐姫のかるた大会なども活発に行われている地である。
さらに小浜の北川の河口近くにある釣姫神社の由緒書きには、
承安二年(1172)に讃岐が愛用した面が福谷の海岸に漂着したので、
その面を神宝とし、併せて讃岐の御神霊を勧請して祀ったと書かれている。
また、この神社は田烏の釣姫明神から移転されたものであるという話も伝わる。
古い伝説に近いことなので、よく分からない部分も多いが、
人を非難することをしなかったと言われる讃岐が、
時代を超えて多くの人々に愛され続けたであろうことは、このことからも窺える。
国立舞鶴高専名誉教授
文学博士 村上 美登志