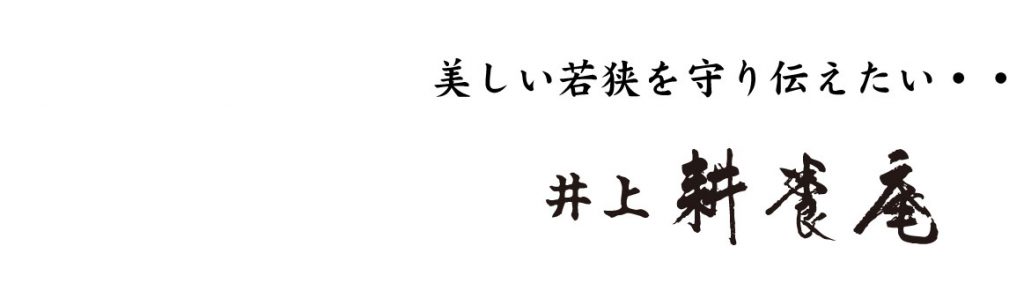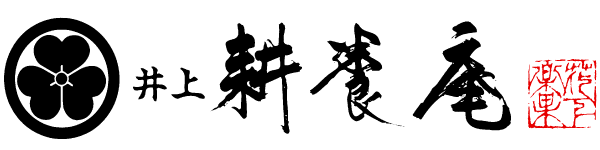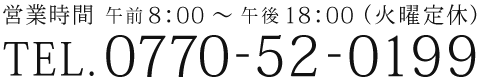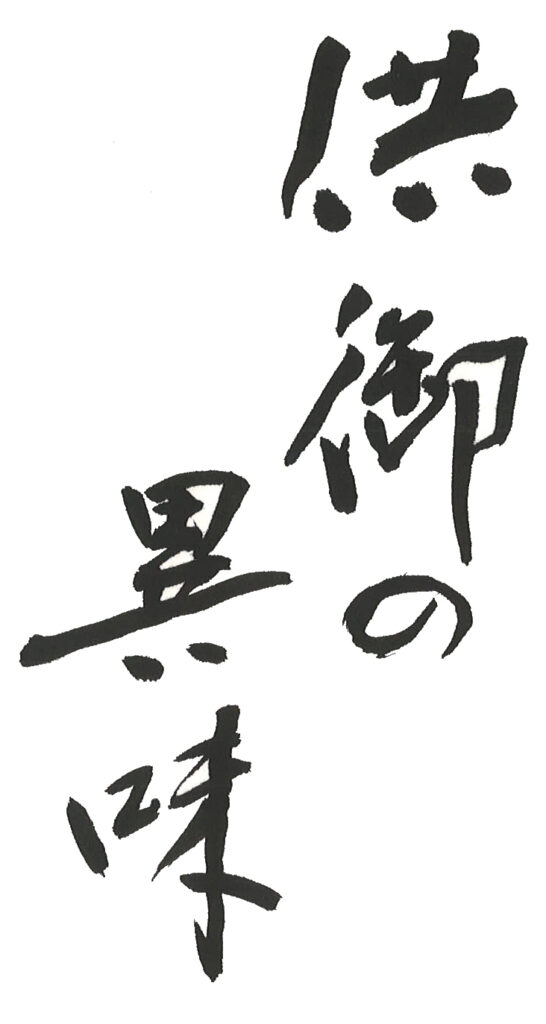
若狭・近江・紀伊・淡路・伊勢・志摩の五国は、
古代において毎月「供御の異味(天皇の食物たる珍味)」を
伝統的に貢進する国でした。
『東大寺要録』には、聖武太上天皇が亡くなってから三七日に当たる日に、
娘の孝謙天皇から「聖武の冥福のために供御の貢進を停止する」と、
勅が出されています。聖武亡き後のことですから、
天皇への珍味は植物ではなく魚介類や肉類、
つまり生き物であったことが推察できます。
奈良の都(藤原京・平城京)からは、
贄(天皇への山野河海の貢納物)を貢進していた木簡が出土しています。
発掘資料では二十八国の贄木簡が出土しており、
平安時代の『延喜式』(法令書)には、
贄を貢進する国が四十か国以上あります。
このことから、
贄を貢進する国が御食国に相応するわけでないことが分かります。
御食国の特性として、志摩・淡路、若狭のように、
古代においていずれも一国二郡の小国で、
可耕地に恵まれない小国が多いのです(若狭は、遠敷・三方郡)。
つまり、御食国は、海の幸に恵まれていたことで存在し得たのです。
『万葉集』には、御食国として淡路や伊勢・志摩が詠まれています。
同じ条件下にある五国は、いずれも御食国と言えます。
さらに、若狭に関わることでは、
古墳時代の首長(王)が 膳 氏であることや、
平安時代初期のこととして、宮中の内膳司(長官)に膳氏から改姓した
高橋氏が任ぜられています。
若狭は、古墳時代には大王家に、
奈良・平安時代には天皇家に海産物を貢進することで、
宮中と深く関わっていたのです。
現在、福井県の特産品として、
若狭カレイ・福井梅・越前蟹などが宮内庁に献上されています。
性格はまったく違いますが、その遺制(名残り)でしょうか。
関西大学 講師 博士(文学) 入江文敏