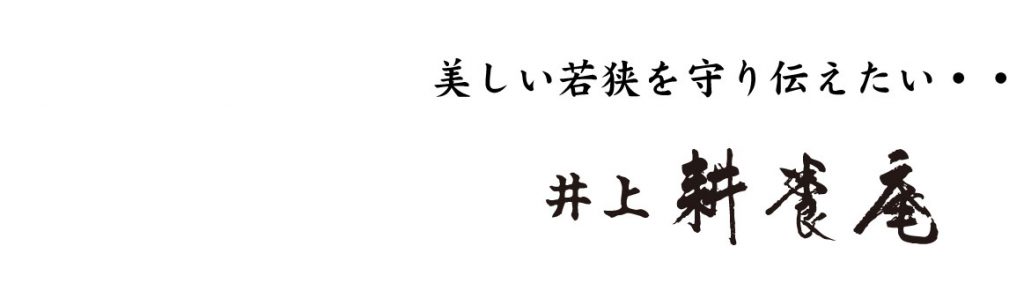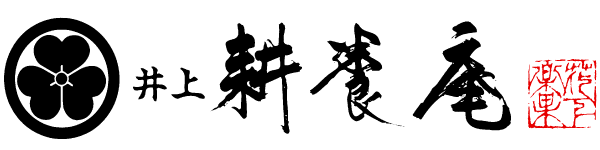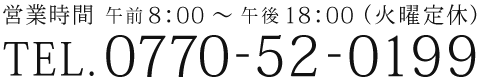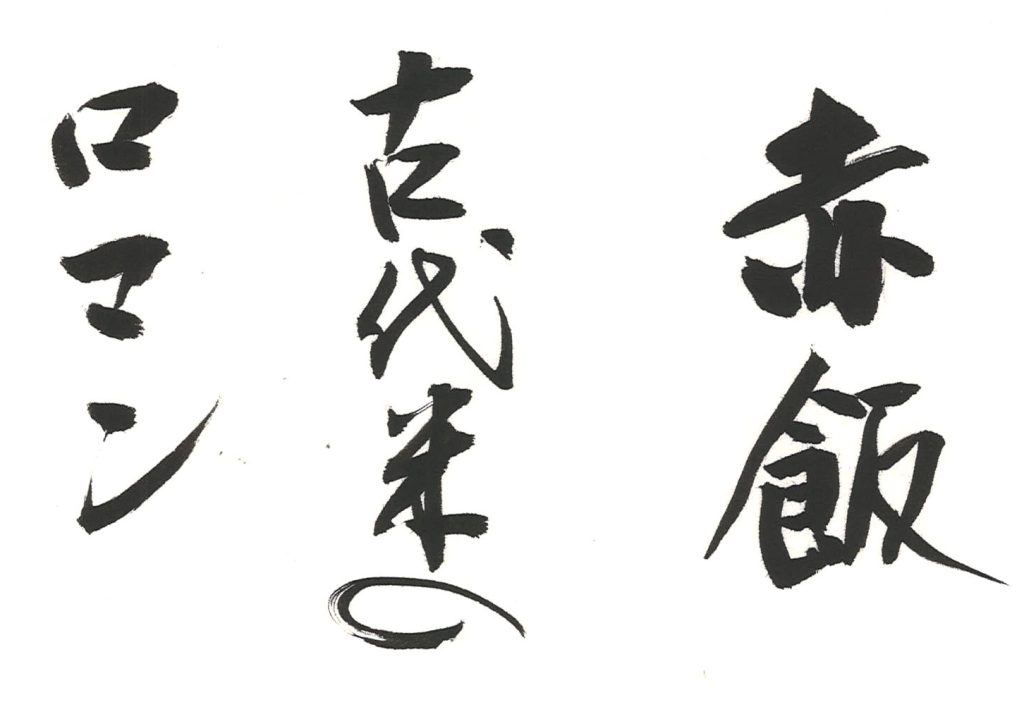
赤米や黒米など古代米をつくっている友人から、
今年は紫黒米(さよむらさき)という米をいただきました。
白米に少し混ぜて炊くと、薄紫色のきれいなご飯になります。
日本に稲作が伝わったのは縄文時代の終わり頃といわれています。
そのころの米は黒米や赤米だったそうです。
米の伝来によって人々は食料不安から解放されることになりました。
人口が急速に増えるなかで弥生時代を迎えます。
命の綱である米を日照りや洪水などから守ってくれるよう
神々に祈ってきた人々は、
秋の収穫を終えると感謝のお供えをしたことでしょう。
お供えは赤米を炊いた赤飯だったと思われます。
今でもお祝いのお供えが赤飯であったり、
紅白のお餅であるのは古代から続く習わしのように思えてなりません。
もし、ドラエモンのタイムマシンを借りることができたら
卑弥呼の時代にタイムスリップして、
どんな暮らしをしていたのか見てみたい。
古代米のご飯をいただきながらそんな思いをつよくしています。
来年はどんな古代米がいただけるのか、
古代へのロマンに浸りながら一年も先のことを楽しみにしています。
池河内 川畑哲夫